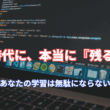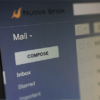【非エンジニアも必見】AI時代に価値を高めるWebエンジニアの「技術力+非認知スキル」
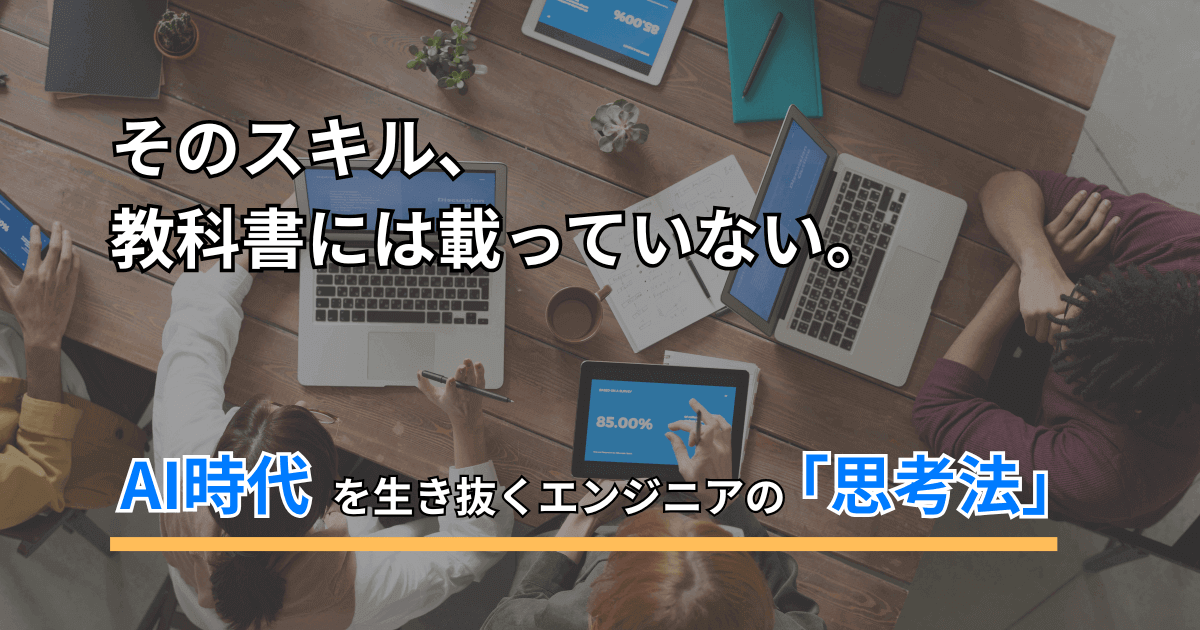
新しいスキルを身につけようとするとき、多くのWebエンジニアは、プログラミング言語の文法やフレームワークの使い方といった、教科書に書かれている知識から学び始めます。もちろん、高品質なコードを書き、堅牢なシステムを構築するための技術力は、Webエンジニアにとって最も重要な土台です。それは、まるで建物を建てるための設計図を手に入れるようなものです。
しかし、設計図通りに建てた建物が、必ずしもユーザーにとって使いやすいとは限りません。風通しや動線、そして住む人の感情といった、設計図には描かれない大切な要素があるからです。
私自身、Web制作の現場や、DX推進のコンサルタントとして企業に関わり、そして大学で教える中で、この「描かれない部分」こそが、一流のエンジニアとそうでないエンジニアを分ける最も重要な要素だと気づきました。
そして、これはWebエンジニアだけの話ではありません。
例えばマーケティングの世界では、AIが広告文をいくら生成しても、人の心を動かすブランドの「世界観」を考えるのは人間の仕事です。同様に、AIがあらゆるデータを分析できても、最終的にどの事業に投資するかの「覚悟ある決断」を下すのは経営者の役割です。
そして、このことはノーコード / ローコードツールや生成AIの登場によって、より一層明らかになりました。
これらのツールは、まるで史上最高の「設計士」のようなものです。膨大なデータから最適な設計図(コード、文章、分析方法など)を瞬時に提示してくれます。
しかし、これらのツールにはまだできないことがあります。それは、「何のために建てるか考える」「ユーザーの心に寄り添う」「周囲のビジネス環境を読み取る」といった、人間ならではの「非認知スキル」なのです。
ここでは、Webエンジニアとして、そして教育者として、私が最も大切だと感じている非認知スキルを3つ、具体的なエンジニアリングの事例を交えながら説明していきます。
1. 問いを立てる力(真の課題発見力)
教科書や技術書は、与えられた問題を「どう解くか(How)」を教えてくれます。しかし、実務で本当に重要なのは「何を解くべきか(What)」を見極めることです。
例えば、プログラミングのチュートリアルでは「この機能を作成せよ」と明確なゴールが設定されています。しかし、現実のプロジェクトで「Webサイトの読み込みが遅い」という課題が挙がったとき、あなたならどうしますか?
多くのエンジニアは、すぐに画像の圧縮やサーバーの増強といった「How」に飛びつきがちです。
しかし、本当に価値のあるエンジニアはこう問いかけます。
- 「なぜ、読み込み速度を改善する必要があるのでしょうか?」
- 「ユーザーは、本当に読み込み速度にストレスを感じているのでしょうか?それとも、別の部分に課題があるのでは?」
もしかしたら、本当の課題は「ページのコンテンツが魅力的でない」ことかもしれず、速度改善は根本的な解決にならないかもしれません。
ノーコード / ローコードツールや生成AIは、問いが明確であればあるほど、その力を最大限に発揮します。 しかし、その問い自体がズレていては、どれほど優れたツールを使っても、価値のあるものは生まれません。
エンジニアの役割は、ツールを使いこなすこと以上に、その力を最大限に引き出すための「良質な問い」を立てることです。
2. 専門用語を「日本語」に翻訳する力
エンジニアにとって、プログラミング言語や専門用語は共通言語です。しかし、クライアントや他部署のメンバーにとっては、まるで外国語のように聞こえてしまいます。
どれほど優れた技術力を持っていても、それが相手に伝わらなければ、プロジェクトは円滑に進みません。特に、ノーコード / ローコードツールが普及し、非技術者も開発に参加するようになった今、エンジニアには「翻訳者」としての役割が、より一層求められています。
例えば、新しい機能を実装する際、「サーバーレスアーキテクチャを採用することで、インフラコストを大幅に削減できます」と説明しても、クライアントはピンとこないでしょう。
しかし、このように伝えたらどうでしょうか?
「今回の新機能は、水道の蛇口のように、使った分だけ料金が発生する仕組みで作ります。なので、アクセスが少ない時間帯のコストはほぼゼロになり、無駄な出費を大幅に抑えられます。」
このように、難しい概念を身近なものに例える「翻訳力」は、相手の理解を深め、安心感と信頼を築く上で不可欠です。技術者は「何ができるか」を伝える翻訳者としての腕を磨くことで、プロジェクトを成功に導くことができます。
3. 「見えない力」を可視化する力
プロジェクトは、仕様書やタスクリストといった「目に見える情報」だけで動いているわけではありません。
- チームメンバーのモチベーション
- クライアントが抱える、言葉にならない不安
- 部署間のコミュニケーションの円滑さ
これらは、プロジェクトの成否を大きく左右するにもかかわらず、簡単には観測できない「見えない力」です。
生成AIは、膨大なデータから相関関係を見つけ出すことは得意ですが、チームの空気感や、顧客の表情から「何かおかしい」と感じ取るような、人間的な洞察力はまだ持てません。
例えば、ある機能開発の進捗が遅れているとしましょう。タスクリストの遅延だけを見て「なぜ遅れているんだ」と指摘するのは簡単です。しかし、一流のエンジニアは、その裏に潜む「見えない力」を可視化しようと試みます。
- 「チームメンバーは、この機能の意義にワクワクしているか?」
- 「技術的な課題の他に、コミュニケーションで何か問題は起きていないか?」
- 「顧客は、本当にこの機能を望んでいるのだろうか?」
これらの問いを立て、観察と対話を通じて「見えない力」を把握し、それに対処する能力こそが、人や組織を動かす鍵となります。これは、データ分析やプログラミングといった合理的な思考だけでは決して得られない、人間ならではのスキルです。
AIで「差がつく人」と「差がつかない人」の決定的な違い
AIの登場で、多くの人が同じように便利なツールを手に入れました。しかし、これからはAIを「どう使うか」によって、エンジニアの間に大きな差が生まれていきます。
では、「差がつく人」と「差がつかない人」の違いは一体何なのか。それは、AIとの関わり方にあります。
- 差がつかない人:AIを「便利な検索エンジン」として使う
- 何か知りたいことがあると、AIに質問を一つ投げ、返ってきた答えをそのままコピーして使う。これは、従来の検索エンジンが少し賢くなった程度の使い方です。確かに作業は少し速くなりますが、それ以上の成長はありません。むしろ、AIが生成したコードの意味を理解しないまま安易に使い続けるのは、スキルが停滞するだけでなく、気づかぬうちにバグを埋め込んでしまう危険性もある、最も避けるべき使い方です。
- 差がつく人:AIを「良き相談相手」や「思考を深めるパートナー」として使う
- AIに質問を投げ、返ってきた答えに対して「本当にこれがベストな方法?」「他に5つの選択肢を提案して」「このコードのセキュリティリスクは何?」と、さらに深い問いを投げかけます。AIを自分の思考を広げ、深めるためのパートナーとして活用し、対話の中から一人ではたどり着けなかった最適解を導き出すのです。
この「良き相談相手」としてAIを使いこなすために必要なのが、まさにこれまで説明してきた「問いを立てる力(非認知スキル)」であり、AIの答えを正しく評価するための「深い技術力」になります。
AIは、受け身で使う人にはそれなりの答えしか返してくれません。しかし、主体的に関わる人には、最強の思考パートナーとして応えてくれます。
なぜ技術力が不可欠であり続けるのか
AIの進化は目覚ましく、多くの定型的なコーディングは自動化されるでしょう。しかし、それはエンジニアの仕事がなくなることを意味しません。むしろ、AIという強力なツールを使いこなし、より高度な価値を生み出すために、技術的な基礎体力はこれまで以上に重要になります。
AIはあくまで「優秀な副操縦士(コパイロット)」であり、私たち人間は最終的な責任を負う「機長(パイロット)」です。
具体的には、AI時代のエンジニアには、主に以下の3つの役割が求められます。
- AIの「最終監査役」
- AIは平気で間違ったコード(ハルシネーション)を生成します。そのコードが本当に正しいか、セキュリティに問題はないか、そしてなぜそのように動作するのかを深く理解し、検証・修正する。この品質と安全性を最終的に担保するのは、間違いなく人間のエンジニアです。
- システム全体の「設計者」
- AIは部品(コードスニペット)を作るのは得意ですが、家全体(システムアーキテクチャ)を設計することはまだできません。どの技術を選び、将来の拡張性を見越してどのように全体を組み上げるかという上流工程の意思決定には、人間の幅広い知識と経験に基づく判断が必須となります。
- AIの能力を引き出す「指揮者」
- AIから質の高いアウトプットを引き出すには、質の高いインプット(指示・プロンプト)が不可欠です。プログラミングの原理を本質的に理解しているからこそ、「どのような指示を出せば、AIが最適なコードを生成してくれるか」を的確に言語化することができます。
このように、非認知スキルが目的地を指し示す「コンパス」だとすれば、技術力は目的地へたどり着くための強力な「エンジン」です。コンパスだけでは、前に進むことはできません。
技術力と非認知スキル、この両方を掛け合わせることで初めて、私たちはAI時代においてAIには真似できない、自分の価値を生み出せるわけです。
AIは価値を再定義する
ノーコード / ローコードツールや生成AIの登場は、私たちWebエンジニアから「教科書的な知識を覚える仕事」を奪うかもしれません。しかし、それは悲観することではありません。むしろ、人間が本来得意とする「非認知スキル」を磨くための時間を、テクノロジーが作ってくれていると考えてください。
忘れてはならないのは、これらの非認知スキルは、技術力という土台の上でこそ輝くということです。
生成AIは、根拠のないことを自信満々に提案したり、一見すると正しそうでも誤ったコードを生成する「ハルシネーション」を時として起こします。だからこそ、コードを正しく読み、システムの仕組みを深く理解している人間のエンジニアがその真偽を見抜き、的確な「問い」を立て、本質的な「翻訳」を行うことが不可欠なのです。
コーディングスキルが不要になる時代は、おそらく来ないでしょう。むしろ、AIを使いこなし、事業の根幹に関わるような複雑な課題を解決できる、一握りの高度な技術者の価値は、ますます高まっていくはずです。
これからのエンジニアに求められるのは、技術力と人間的な洞察力を掛け合わせ、AIには生み出せない価値を創造することです。表面的な要望の奥にある本質的な課題を見つけ出すために問いを立て、専門知識を誰にでもわかる言葉に翻訳して人との信頼関係を築き、そして人や組織を深く理解するために見えない力を可視化する。
これらは教科書や座学ではなく、日々の開発やチームとの対話の中でしか磨かれない、極めて人間的なスキルです。
「コードを書く人」で終わらないよう、ぜひ今日からこれらのスキルを意識して仕事に取り組んでみてください。
この記事で述べた「技術力」について、Webデザインやプログラミングの「学習」に焦点を当てた内容も以下の記事でお話しています。AI時代に本当に価値を持つ「基礎スキル」を解説していますので、ぜひ読んでみてください。